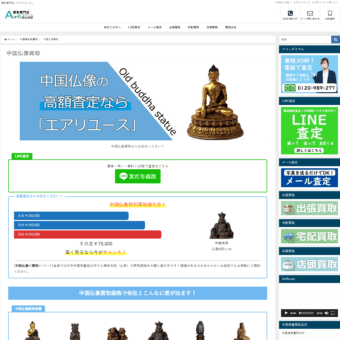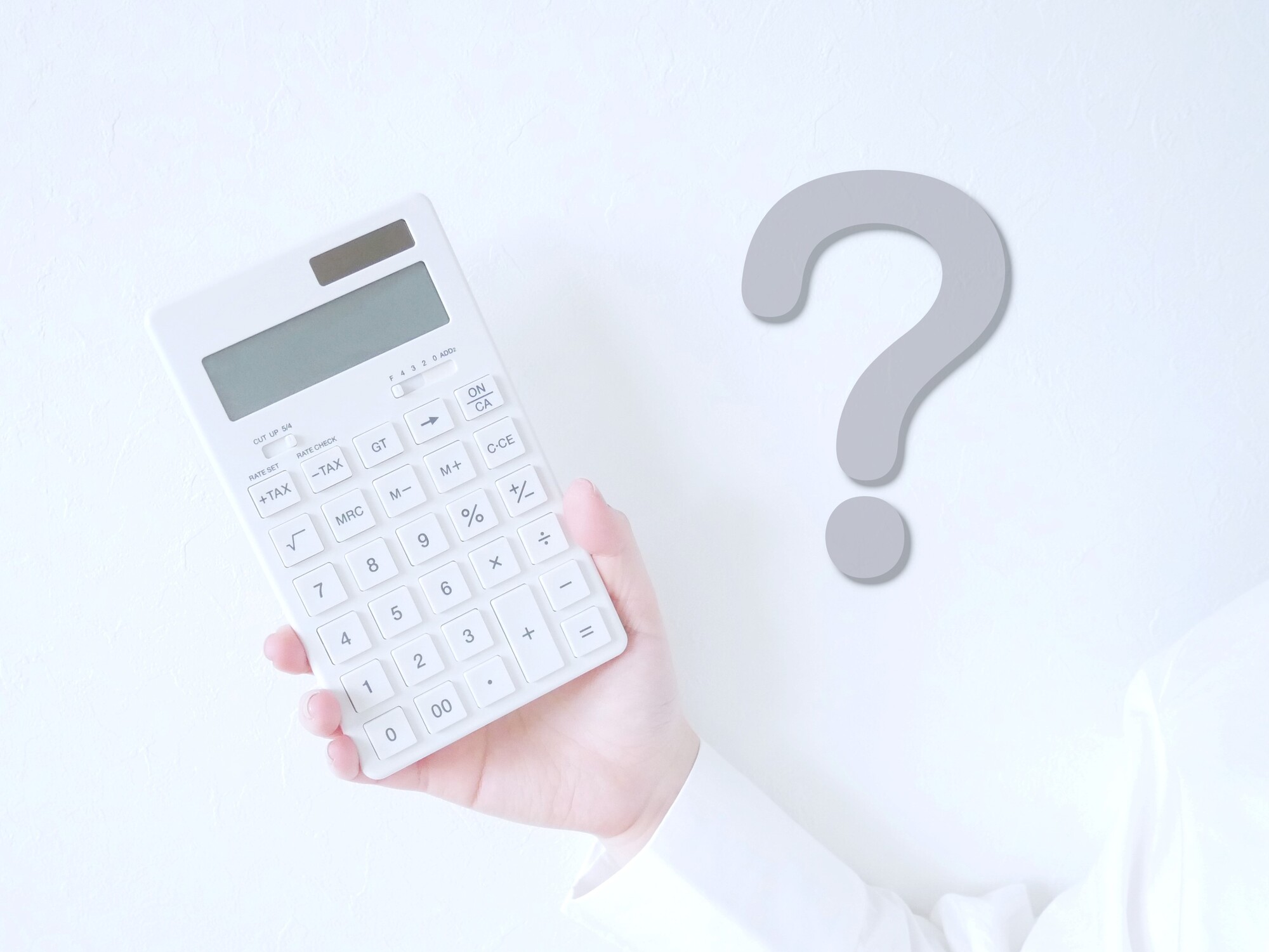彫刻仏像とは?美と精神性を表現する芸術の魅力と歴史を解説!

彫刻仏像とはおもに、ブッダおよび仏教の諸尊像を造形的に表現した彫像のことを言います。仏教を解くうえで重大な役割を持っており、古代から現代まで、信仰の対象としてだけでなく、芸術作品としても人々に感動を与え続けているのです。この記事では信仰と芸術が融合し、美と精神性を表現するようになった彫刻仏像について解説していきます。
仏像彫刻の歴史と意義の探求
仏像彫刻の歴史は、仏教の伝播とともに多様な文化と芸術が、交錯しつつ発展してきました。
初期の仏像は釈迦の姿を拝むために制作されましたが、偶像崇拝が憚られたため、足環や菩提樹などで象徴的に表わされていました。
そしてアレクサンドロス大王の東方遠征により、西方のギリシャ文化や古代オリエント文化における彫刻の文化がもたらされるようになり、この時代から仏像が作られるようになりました。
そして日本では飛鳥時代に中国や朝鮮半島を経由して仏教が伝わり、同時に仏像も作られるようになったのです。奈良時代になると、国家が寺や仏像の建立や造営などに力を入れたこともあり、さまざまな技法で、写実的かつ美しい仏像が多く作られるようになりました。
平安時代の後期には遣唐使が廃止され、日本独自の文化が花開くと同時に仏像もまた、日本独自の進化を遂げていくことになったのです。
彫刻技法と素材の選択による表現の多様性
日本には、木像、石像、塑像、乾漆像、金銅像といった種類の仏像が存在します。
それらの個々の特徴や技法について解説していきます。
木像
飛鳥時代から仏像には木材が使用されてきました。
ひとつの木から仏像を彫り出すのを「一木造」といい、複数の木を寄せ集めて体の各部をそれぞれ別の木で作り、それを寄せ集めてひとつの仏像を彫り出すのを「寄木造」といいます。材料は、ヒノキ・マツ・クスノキ・カマチ・ツゲ・カヤ・ビャクダンなど多岐にわたります。
そして平安時代以降は木像が主流となっています。そして、経年によって自然に色味が変化し、時間と共に仏像に味わい深さが増すのも特徴のひとつであり、さまざまな仕上げ方や技法があります。
木の質感そのままの無彩色の仏像や、鮮やかな彩色が施された仏像など、どちらにも異なった魅力があるのです。
石像
海外とは異なり、石を材料にした仏像は彫刻に適した石が少ない日本ではそれほど普及しませんでした。
切り出された岩だけでなく、自然の中の岩山などに掘ることもあり、それらは「摩崖仏」と呼ばれています。そして独立した石に仏像を彫刻したものを「単独像」と呼びます。
江戸時代には民間信仰と結びついた、素朴な地蔵菩薩像などの石仏が路傍や鎮守の森に安置され、現代でも全国各地で見られるのです。
塑像
粘土で造られた仏像のことを塑像といいます。
主に奈良時代に流行した技法で、まずは簡単な木の芯に縄を巻き、その後粘土で作り上げていく方法です。
造形の自由度が高くきめ細やかに仕上がり、手間や費用もかからないという長所がある代わりに、粘土で作った後は焼かずに仕上げるため、湿度の影響を受けやすく保存が難しいという難点と、重く壊れやすい欠点もあります。
乾漆像
乾漆像には「木心乾漆」「脱乾漆」の2種類があります。
豊かで弾力がある質感と微妙な雰囲気を出すのに効果的な技法です。「木心乾漆」は、粗削り程度に形を彫り上げた木彫りの像に漆を、1センチほどの厚さに盛り付けて塑像したものです。
「脱乾漆」は芯に粘土を盛り付けて像の形をつくり、漆を接着剤に麻布を何重にも張り重ねて、乾いてから布を切開し内部の粘土を取り去る方法です。主に奈良時代に流行しました。
金銅像
蝋と土で出来た型に溶けた金属を流し込んで鋳造する方法です。
なめらかで艶があるのが特徴です。主に加工がしやすい銅が使われましたが、のちの時代には鉄や金、銀なども使われています。奈良の東大寺の大仏や鎌倉の大仏もこの方法で造られました。
鎌倉時代には身体の各所を別々に鋳造して組み合わせる「吹き寄せ法」も多く用いられるようになりました。
仏像彫刻の鑑賞と制作における深い精神性と美の追求
仏像づくりは飛鳥時代から昭和中期ごろまで、仏師という専門職の人々が作るものであると一般的には認識されており、自分で仏像を彫ることは無理だと思っている人も多くいました。
しかし近年ではカルチャーセンターや寺院などで開かれる教室で、手のひらサイズの仏像を制作することもできるようになりました。仏像を彫るということは、仏の精神を彫るということに繋がるため、仏像彫刻は単なる彫刻とは異なっているのです。
仏像を彫る仏師たちは時代の流行に関係なく、ただひたすら目的の仏像を作ることに精魂をかたむけていたことを忘れてはいけないのです。
まとめ
過去の歴史から学び、現代の美意識で作り出す彫刻仏像の世界には、深い精神性と美の追求が密接に関わっています。それぞれの素材に異なる魅力がある仏像は信仰の対象としてつくられたものであり、つまり祈りの造形なのです。そのため、ただただ美しい芸術作品として見るだけでなく、その背後にある仏教の教えや精神性を理解し、共感すること、そして仏像を作った人々へ敬意が重要なのです。