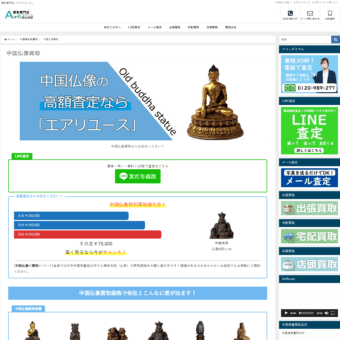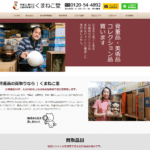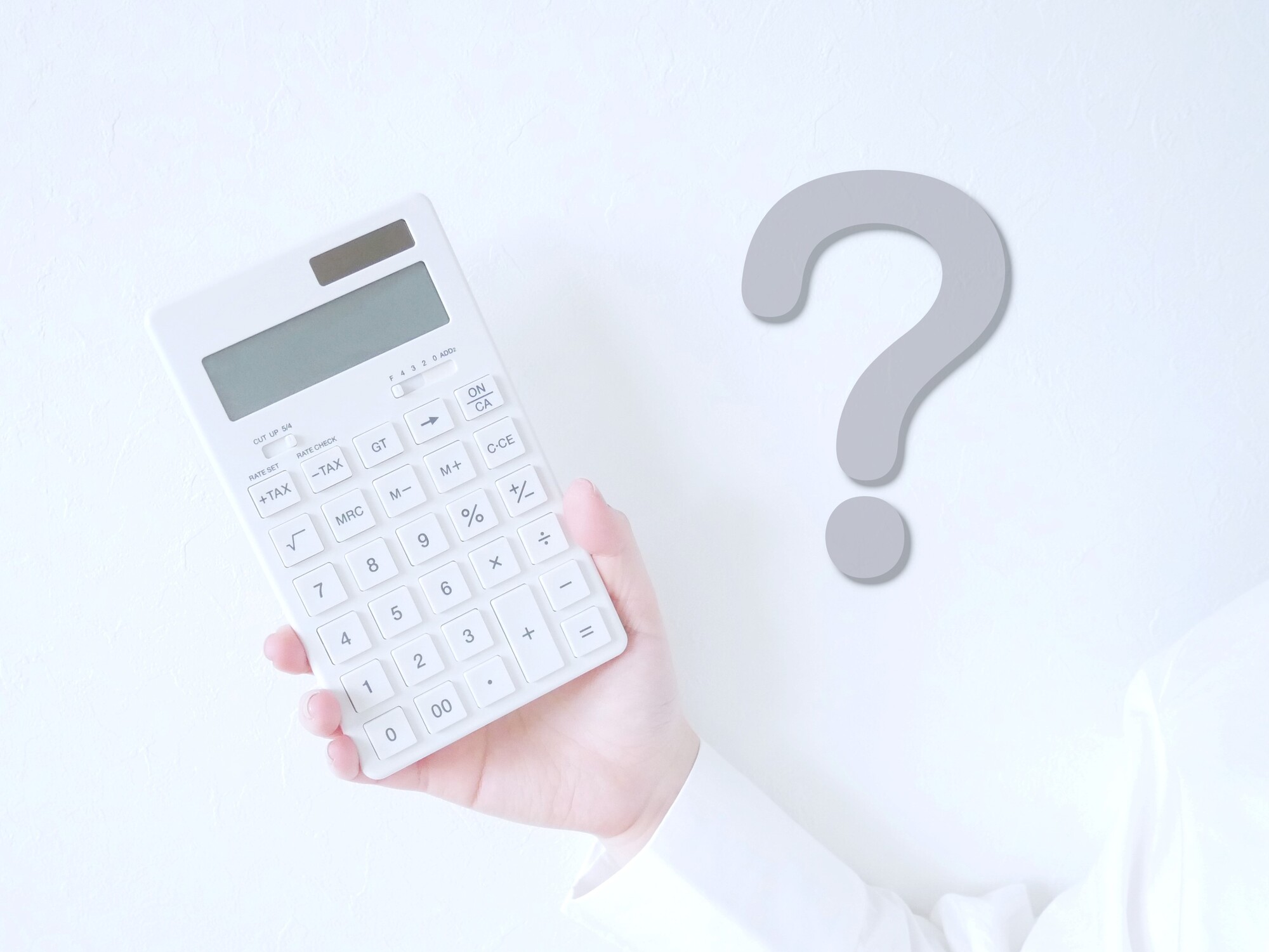仏像の素材にはどのようなものがある?それぞれの特徴について学ぼう!

仏像の素材にはさまざまな種類があるのをご存知でしょうか。この記事では、仏像の素材についてそれぞれの特徴を解説します。また、よい状態の仏像は売却するときも高値が期待できます。傷みや劣化を防ぐためのメンテナンス・保管方法もぜひ押さえておきたいポイントです。査定に出す際に高値がつくコツについても紹介しましょう。
仏像の素材ごとの特徴
国内にある仏像は、素材によって5種類に分けられます。まずは、それぞれの素材ごとにどんな特徴があるのか解説します。
金属
一言で金属製の仏像といっても、金、銀、銅、鉛、錫、鉄など、さまざまな金属で作られているようです。最も多いのは、溶かした青銅で形を作り、上から金メッキを施した金銅仏と呼ばれる仏像です。有名な奈良の大仏も金銅仏です。
また、最も高値で売却されるのが金でできた仏像となります。高価な物はなんと数百万円の値段がつきます。さらに金の価格が高騰している時は、金の仏像も価値が上がるようです。高値で売却したいなら、金の価格の変動にも注目して査定に出してみましょう。
木造
森林資源が豊かであったこともあり、国内にある仏像の多くが木彫りの仏像です。ヒノキが多いですが、カツラ、サクラ、カヤ、白檀、黒檀で作られた仏像もあります。一本の木から作る一木造(いちぼくづくり)と、いくつかの木材を組み合わせた寄木造(よせぎづくり)の2種類に分けられます。
一木造の仏像は、奈良時代末期から平安前期に作られた作品が多いのが特徴です。それ以降の時代に作られた仏像の大半は寄木造です。そのため、一木造の仏像の方が古い作品が多く、査定でも高値が期待できます。
石造
石でできた仏像には2種類あります。切り取った石を彫った仏像は独立像と呼ばれます。また、岩山に直接彫られた石仏は摩崖仏と呼ばれているようです。摩崖仏は日本各地で観光名所ともなっています。
個人所有できるのは独立像だけであり、今も現存する独立像の約8割が江戸時代に作られています。一般的に古い時代に作られた仏像は価値が高くなるようです。しかし石仏の場合は、古くに作られたものでも査定価格は抑えめであることも特徴です。
乾漆造
粘土や木で作った原型の上に、麻布を漆で貼り付けて作った仏像です。乾漆の仏像は7世紀から9世紀までに多く作られました。全体的に柔らかな印象の仏像を生み出すのが漆の特徴です。
塑造
木で組んだ骨組みを縄で巻き、上から粘土を塗って肉付けするのが塑造の仏像です。日本では主に天平時代に作られました。
仏像のメンテナンス・保管方法
仏像がよい状態であれば、査定でも高値が期待できます。そこで、仏像のメンテナンス方法と保管方法について解説しましょう。どの素材の仏像でも、メンテナンス方法と保管方法は共通です。
メンテナンス
仏像を触る時は手袋をはめましょう。乾いた柔らかい布や、毛先の柔らかい刷毛や筆を使って汚れや埃を取り除いてください。絶対に水拭きは避けましょう。とくに細かい部分は繊細なので、力を入れずにとくに慎重にお手入れします。カメラレンズを手入れする際に使うブロワーや綿棒などで優しく埃を取ってください。また、虫干しする時は日陰で干します。
保管方法
保管するときは直射日光と高温多湿を避けてください。紫外線は変色や塗装が剥げる原因となるので、絶対に直射日光に当たらないようにしましょう。できれば専用の木箱に入れて安全な場所に保管します。とくに木の仏像は、温度と湿度が一定になるよう注意してください。湿度が高いとカビが発生し、乾燥しすぎると変形やひび割れが起きます。
仏像を高値で売却するテクニック
それでは、どうすれば仏像を高値で売却できるのでしょうか。簡単なテクニックを2つ紹介します。
鑑定書
仏像の鑑定書があれば必ず一緒に査定に出しましょう。鑑定書とは、その仏像がどのような作品であるかを第三者が証明した書類です。査定をする側にとっても、鑑定書があれば安心して買取りできるのです。また、古美術店やデパートなどで購入しているなら、領収書などの証明できる書類を探してみてください。
付属品
共箱と呼ばれる専用の箱がついていれば、査定額アップが期待できます。共箱には作者の印がある場合が多いからです。実は仏像には贋作も多く存在するため、本物の作品であることを証明できる共箱があれば有効になるのです。台座や保証書もあれば、必ずセットで査定してもらいましょう。
仏像の素材にはどのようなものがあるのか、それぞれの特徴について解説しました。制作された時代によっても、仏像の素材はさまざまです。また、素材によって仏像の持つ印象や価値も異なることを紹介しました。仏像の劣化を防いでよい状態に保つためには、定期的なメンテナンスと適切な保管が大切です。鑑定書や付属品があれば高値での売却も期待できるので、大切に保管しておきましょう。