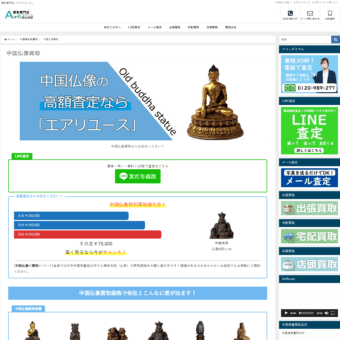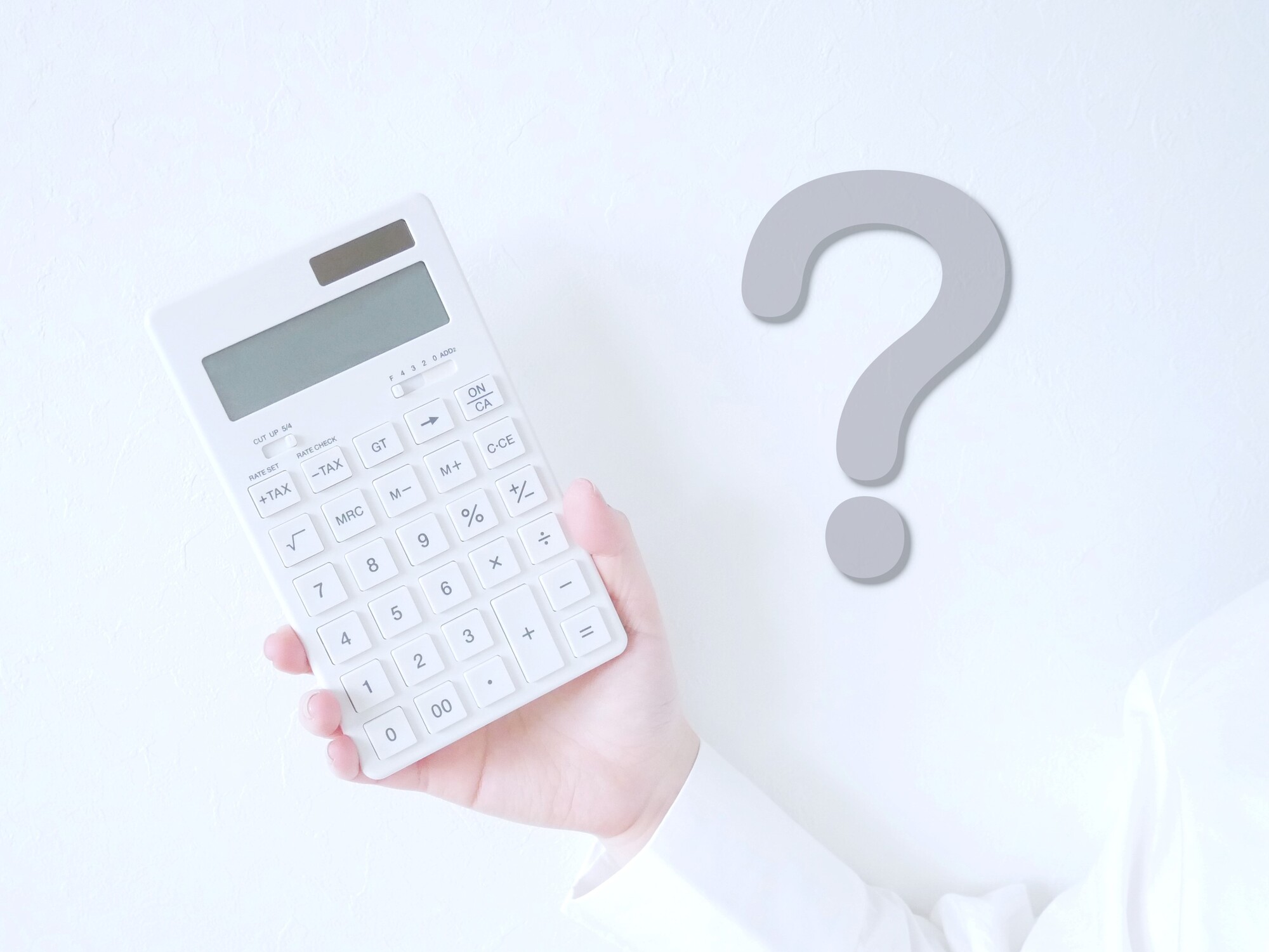仏像の素材にはどのようなものがある?種類ごとの特徴を解説!

仏像には、大きく分けて5種類の素材があります。それぞれの素材によって、作り方や魅力が大きく異なります。この記事では、仏像の素材や種類について詳しく解説します。
木造の仏像の特徴
木造の仏像は時間が経つにつれ、自然に色が変化するのが特徴です。彩色が可能なので、同じ素材・デザインでも違った見た目に仕上げることができます。仏像の原材料となる木材の種類も豊富にあり、飛鳥時代にはクスノキ、それからはヒノキやカヤが使われてきました。また、木造で仏像を作る際は、主に「一木造り」と「寄木造り」どちらかの技法を使います。それぞれどのような技法なのか見ていきましょう。
一木造り
一本造りとは、一つの木から一つの仏像を作り出す技法のことをいいます。主に奈良時代末期から平安時代前期の仏像は、一木造りで作られたものになります。
寄せ木造り
寄せ木造りとは、複数の木を寄せ集め、一つの仏像を作り出す技法のことを言います。こちらは、一木造りよりも新しい技法であり、平安時代以降の仏像が、寄せ木造りで作られたものになります。
塑像の仏像の特徴
塑像(そぞう)の仏像は、粘土や石膏を原材料として作ります。塑像は中国の唐時代に盛んに作られ、日本にも技術が伝えられました。日本の塑像の技法が伝わったのは7世紀末ごろ。その後8世紀を中心に、数多くの作品が残されています。
塑像で仏像を作る際は、木心(もくしん)に荒縄などを巻きつけ、目の細さが異なる土を盛りつけていきます。土を盛りつけていく作り方なため、失敗しても作り直しができ、材料も安価で済みます。しかし、中が空洞ではないため、重さがあり、壊れやすいという欠点もあります。
乾漆の仏像の特徴
乾漆造とは、和紙や麻布を漆で塗り重ねることや漆と木粉を練り混ぜたものを盛り上げ作られた仏像のことをいいます。主に7世紀から8世紀の作品が多く、それ以外の時代にはあまり見られない技法です。乾漆造は脱活乾漆造と木心乾漆造に分けられます。それぞれどのような技法なのか見ていきましょう。
脱活乾漆造
脱活乾漆造とは、土で作った原型に麻布を漆で貼り重ねていき、成形する技法のことをいいます。原型作りでは、木組みを作った上に藁縄(わらなわ)を巻き、土を塗りつけていきます。その後、さらに目の細かい砂や紙の繊維などが混ざった土を、ヘラを使って造形することで原型が完成します。
完成した原型には、接漆と麻布を貼り重ねていきます。麻布の貼り重ねを終えた後は、仏像の後頭部と背中の部分の麻布を切り取り、中の木組みと土を取り除いていきます。
中の木組と土を取り除いてしまうと仏像が空洞になってしまうため、像を支える木組みを入れていきます。中に入れた木組を像の外側から釘で固定し、最後に麻布を取りの板ことでできた開口部に木屎漆を盛り付けて完成です。塑像とは違い中身が空洞であるため、重さもなく壊れにくいというメリットのある技法になります。
木心乾漆造
木心乾漆造とは、木彫りの像を原型とし、木屎漆と漆を盛り上げて細部まで仕上げる技法のことをいいます。木心乾漆造は木彫りの像を原型として使うため、完成までの手間が省けます。また土を使わず、漆を使う量も少なくなるため、制作費も削減することが可能です。しかし、乾漆の塗り方次第ではひび割れができてしまうなど、高度な技術が必要とされる技法です。
金属製の仏像の特徴
金属製の仏像は、金・銀・銅・鍮石・白蠟・鉛・錫・鉄・青銅などさまざまな金属で作られているのが特徴です。溶かした青銅で形を作り、その上にメッキを施した金銅仏といわれる仏像は、最も多く作られています。日本だけでなく、インドや中国などでも金銅仏は作られています。日本に初めてきた仏像も金銅仏の釈迦如来であり、日本の仏像のルーツを作ったともいわれています。誰もが知っている奈良の大仏も、金銅仏で作られている仏像です。
石で作られた仏像の特徴
石で作られた仏像は、マトゥラー仏やガンダーラ仏など、初期仏教の作品に多く見られます。日本では江戸時代ごろに多く作られており、石仏の8割が江戸時代に作られた作品といわれています。
しかし日本には彫刻に適した石が少ないため、現在ではあまり見られません。また石で作られた仏像には、切り取った石を彫り作られた独立像、自然にある岩山に直接彫って作られた磨崖仏の2種類があります。
仏像にはさまざまな種類があります。素材や時代によって、作り方が大きく異なることがおわかりいただけたでしょうか。仏像は素材だけでなく、表情や表現手法などにも違いがあります。その意味を知って仏像を見てみると、より仏像に興味が沸いてくるはずです。仏像は信仰の象徴であるとおもに、知れば知るほど魅力を感じられる芸術作品でもあります。ご自宅に眠っている仏像はどのように作られているのか、どのような存在でどんな意味をもっているのかを調べてみると、新たな仏像の魅力を感じられるかもしれません。